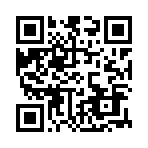2016年08月03日
フエルトスパイクとフエルト

タフな作りが売りですね。
鮎用のシューズやタビを見ているとフラッグシップに該当するものほとんどにソールはフェルトスパイクが搭載されていますね。
ところが渓流用としてはフェルト底がほとんどです。まあ、鮎用・渓流用と明確な分け目はないのですが。
そして以前、渓流釣りより鮎釣りの方が滑るだろう(コケのあるところを釣るから)と思い、ならば鮎用に搭載機が多いフェルトスパイクの方が滑らないのかもと予想し、まだ「ベリピタ」だった時代にソールを貼り替えたことがあります。
が、
実際渓流釣りでは滑る滑るで大変でした。ピンが効きすぎてフェルトまで地面が達していない感じです。なのですぐにフェルトへ戻しました。
んで、以前に川でコケた記事を書いているときに「もしかしてただのフェルトの方が滑らんのでは?」と思い出し、大枚をはたいてソールを購入したので貼り替え作業をします。
現在のソールです。

フェルト部がすり減っているので余計に滑る
そして新品のフェルトソール。

高~い! もうちょっと安くならんかな・・・
まずは「ベリピタロック機構」の「ロック」を外します。

タイラップを切るだけ
そして「ベリ」っとはがします。

とれたフェルトスパイクソール
新しいソールを付属のタイラップとともに合わせながら貼ります。

「ピタ」が結構強力なので比較的慎重に
完成♪

この「ベリピタロック機構」は以前の「ベリピタ」より全然強力に貼り付けることができるので良いです。「ベリピタ」はすぐにベルクロが弱って歩いているうちにソールが無くなってしまうこともありました。
そして使用した感じは・・・
「滑らんなぁ!」
です!
玉石だろうが岩盤だろうがフェルトの方が断然滑りません!
「断然」であって「全然」ではないので、その人の歩き方や別の場所では変わるかもしれませんが私にはフェルトの方が合っていると確信しました。
あ、たぶん草、特に法面などの濡れた草は滑ると思います。
あとは未だにヘタな引き抜きをマスターするだけです・・・。
2015年11月25日
カブラロッド 折れ修理
しかし例年に比べれば遅いですね。
水温も高いようなので波さえ良ければ釣果は望めますが、今週末のレンタルボートの予約は流れそうです・・・。
しかし準備は怠りなくしていきたいものです。なので先日折れた穂先を修理しましょう。

コレですね
ワンピースロッドにつきメーカーでは修理不可です。
しかしネットで検索してみるとそれなりに方法が見つかりました。それを実践していきます。
まずは穂先の処理です。

折れた部分をキレイにします。少しでもキズやバリがあるところはカットし、ヤスリをかけて整えます。

元になる方もガイドと接着されてあるスレッド部を慎重に取り除きます。


次にインナーとなるカーボンの調整です。
素材はホビーショップ等にあるカーボンソリッド(中身の詰まったもの。パイプ:中空でないやつ)を使用します。
折れ口の両方の内径をノギスで測り、キッチリか大き目のものを削って使います。
今回は1.5mm 1.8mm 2.0mm(1本¥400程度)を購入し、1.8mmを使用しました。

ロッドは当然テーパーがかかっていますので、穂先側を削ってテーパーをかけます。

ドリルにはめるとラク
径と長さを調整したところ。

接着には、メーカー的には不安はありますが割と好評なダイソーの2液性エポキシを使います。

元側から接着していきます。乾かすときは逆さまに垂直になるように吊ります。

なぜこのようにするのか? それはエポキシが垂れないように、ロッドとカーボンソリッドの隙間を均等に埋めるようにするためです。

こんな感じ
乾いたら穂先側も同様に接着します。
穂先側はきちっと調整してあるのでスキマうんぬんは元側よりはシビアではないですが、これも垂直に立てて乾燥します。
乾いたらスレッドを巻いていきます。と同時にガイドも巻き込みます。できるだけキレイに。

でもたいしたキレイにはできませんでした・・・。ま、このぐらいで十分です。

そしてその上にエポキシを塗っていきます。
最初は液状ですので垂れてきます。ただ少し粘性があるのと速乾性があるのを利用して、回しながら・塗りながら形を整えます。
ある程度硬化したら薄いゴム手袋の指先に水をつけながら形成します。
・・・ということをやった結果がコレ。

少し太ってイビツですが及第点

見た目そんなに悪くない。
リールをセットしてAFCカブラ(60g)をぶら下げて負荷試験。

曲がりもまあまあ
うん、初めてにしてはいいんじゃない? 上出来!
あとは魚を掛けたときどうなるか、ですね!
2015年03月18日
鮎 根掛かりはずし 自作
鮎釣りってイカリ針がむき出しなので結構根掛かりします。
なのでこういうグッズが販売されていますね。
 【鮎】【ダイワ】鮎 根がかりはずし AN−1110RO (折りたたみ式) |
このショップは結構値引しているのですが基本的に高い・・・。
このオフシーズンにか~なり鮎用品にお金をかけましたので、こだわりのないアイテムはできるだけお金をかけたくない。
よく見ると構造が割と単純なので自作という道に走ったワケです。
準備したものは2mmのステンワイヤー(¥260)とコレ

名前忘れた・・・
¥100均で売っている、先端にマグネットが付いたやつ。
確か自動車整備などでスキマにネジを落としたときに拾う便利アイテムだったと思います。すでにマグネット部は取り外してあります。
まずはこの部分に穴を開けます。

ワイヤーを形成します。
ヘアスプレーなどの缶に巻き付けてキレイに丸くします。

ジョイント部を画像のようにします。

ポール部とビス・ナットを使って接続すると出来上がり♪

65cmまで伸ばせます。

実はコレ、昨シーズンにポール部だけで使用していました。先端がカギ型になっているので比較的浅い場所だと”無いよりマシ”レベルではなく、かなり重宝しました。
すこしチャチですが水の押しが強いところでなけれは全然イケます。
¥500未満で作れるワケです!
押しが強いところや届かないところではこっちを使います。
 タックルインジャパン 根掛かり外し・オトリレスキュー |
これで今シーズンはOKかな?
2014年06月14日
ルアーのお色直し
それにもともとの値段が高い。サスケなんか中古でも色が良ければ結構値が張ります。
なので最近は本当にほしい色のものは新品を買って、そうでないものはボロい中古を買って色を塗り替えてます。
ここで必ず話題になるのが塗装の剥がし方。
ネットで検索すると色々ヒットしますね。
そして多数の方が剥離剤としてアルコール系を使用しているようです。
このアルコール系(イソプロピルアルコール・いわゆるガソリンタンクの水抜き剤の類)、効く塗料のメーカーと効かないメーカーがあるのはご存知ですか?
ある方のサイトに訪問した際にルアーのメーカー別に塗装状態の比較しており、大変参考になりました。
全部剥がれる・上地だけ剥がれる・プラまで溶かしてしまう・・・などなど。
結局私は地道に紙やすりとプラモ用の溶剤を使用するのが一番かなと判断しました。
若干雑にはなりますが使っていればまた痛んで塗り直しになるでしょうから、泳ぎに影響が出ない程度でいいと思ってます。
今回はサスケの95赤金をレッドヘッドに塗り替えます。

中古購入のもの 痛んでます
1.フックを外す。
2.アイを外す。
アイは外す際つぶれてしまうので新品を用意。
3.ヤスる。

私は#240→#400→#600→#1000までやります。
#1000までなのはサーフェーサーが#1000だからです。
4.下地を塗装する。

サーフェイサーの#1000です。
5.ホワイトを塗装する。

6.レッドを塗装する。

7.アイまわりにスモークグレーを塗装。
その後全体にパールを塗装。

アイを強調するため。いわゆるアイシャドウ。パールはお好みで。
8.アイを貼る

径が合えばなんでもいいかと。今回は純正品。
9.セルロースにディッピング。

頭・尻の両方漬ける。
その後乾かしますが、余分な液が垂れてくるのでこまめに除去する。

10.フック(新品)をつけて完成!

あまりこだわらなきゃそんなに難しくないです。
好みによっては下地を塗る前にアルミを貼る・ディッピングを2~3回行うなどアレンジしてみてください。
また、新品購入後にディッピングもアリです。ただ、塗料の分少し重くなります。その影響は確認できておりませんので自己責任で。(私はやってて影響ないです。ないと思います・・・。)
2014年02月08日
電動アイスドリル
やっとHowToの1回目です
今回は電動アイスドリルの紹介です。
とは言っても、結局はtacoさんのブログを拝見して参考にさせていただいた結果なのでエラそうには言えませんです。
さて、
実は2年前に既に電動ドリルは実践しているんです。
その時はブラック&デッカーの14.4V。これにアイスドリルを接続するいわゆる”アダプター”部分を鉄工所勤務のいとこに作ってもらってやってみたんですが、穴1個ようやく開けてバッテリー上がりで終了・・・でした。
そんなに気温は低くなく(-3℃程度)、風もなかったんですが、パワー不足はもちろんですがアダプター自体もセンターが出ていなかったのが原因と思われました。
やはり36Vが必要なのかな~ でも高いな~ 買えないな・・・ ってあきらめていたところに18Vでイケるとの情報を得て、更には手の届く価格であるということが判明。
そして今回から投入したのはこちら。

マキタ DF458D 18V ¥36,000くらいだったと思う


バッテリー2個・充電器・ハンドル・ケースが付いています。
チャック下にはLEDライトが2発付いており、トリガーを引くと光ります。
今は新型のようですね。型番はDF458DRF。
そしてアダプター。”きゃす天狗”で入手。たぶん”釣りの駅”製かと。

¥6,300 昔は他の商品で¥15,000とかだった

この六角の部分に接続

アイスドリルとの接続部。13mmのボルト・ナットです

全長です ドリルは旧型エリクソンMORA

折りたたんだ状態
アダプターもVer.2が出ているようです。
まだ1回しか使っていませんが、バッテリーをポケットに入れてあまり冷えないようにしてポイントまで歩き、-20℃の中で20個以上の穴を開けて、テントの外へ放置しておいても14:00時点でまだ使えました。
この一式を全部そろえるのは結構お金がかかりますが、私がわかさぎを始めた15年前に比べれば用品はだいぶ安くなったし手に入り易くもなりました。
年に1度や2度だけでも、毎年必ずわかさぎに行くんだっていう方は導入するのを強くお薦めします!
年をとって体力がなくなってきた今だから言えます。
一応商品リンク貼っておきますね。
 【木らく部限定!予備バッテリー抜き!】マキタ 18V 充電式ドライバドリル DF458DRF |
そしてこれも更新を考えなければなりません。

自作電動わかさぎ竿
最近は各メーカーからいろんなのが出ましたね~。
こんなのや

ダイワ(Daiwa) クリスティア ワカサギ CR(カウンターリール)2

ダイワ(Daiwa) クリスティア ワカサギ MR(マウスリール)キット

ダイワ(Daiwa) クリスティア ワカサギ SR
こんなの

シマノ(SHIMANO) 12ワカサギマチック DDM プレミアムBセット

シマノ(SHIMANO) 11ワカサギM-DDM
こんなのも

プロックス(PROX) 攻棚ワカサギEC(電動リール)カウンター付

プロックス(PROX) 攻棚ワカサギNC(電動リール)カウンター無
わざわざ自作しなくても手に入り易くなりました。
しかしこれらは自作物より重い。メチャ重って訳ではありませんが、重いと魚の引きが堪能できません。まあ置き竿で掛かって引きずり込まれることは少ないでしょうが・・・。
なのでやはり自作がいいのですが、何年かするとモーターに不具合が出て回らなくなります。
このことから今、モーター換装式のNew電動を目下考案中であります。
完成したらお披露目する予定ですが、あまり期待しないでくださいね・・・。